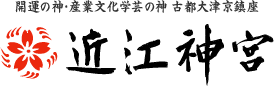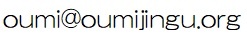令和6年の年柄
令和の御代も六年を迎え、昭和から数えると九十九年、明治では一五七年となる。昭和二十年は明治七十八年だが、昭和二十一年を元年とすると本年は七十九年。今や明治~昭和戦前戦中より戦後の方が長くなった。
新型コロナの蔓延が一段落となり、多くの行事が四年ぶりに通常の態勢で行われたが、復活できないものや変容したものもあり、産業や社会構造の面でもコロナ以前に戻らない面も少なくないと思われ、新型コロナの蔓延は世界史の転換点であったといえるであろう。
本年は一回目の東京オリンピックが行われ、東海道新幹線が開通した昭和三十九年から満六十年。戦後復興を画したこの年から本卦返りを迎えることになった。
その六十年前の明治三十七年(一九〇四)は日露戦争の開戦の年であり、明治体制の絶頂期に至った時期ともいえる。さらにその十年前は日清戦争の開戦の年、十年後の大正三年は第一次世界大戦の勃発の年と、十年ごとに日本にかかわる戦争が起っている。
ウクライナ状勢は長期化、深刻化し、ロシアの所業には憤りやる方ないが、中台状勢への飛び火の懸念もあり、また世界大戦に拡大しかねない不安もあって対応は困難を極める。戦争終結後の復興には日本の戦後復興や震災からの復興の経験が期待されているが、それよりも終結に至る道筋を描くことができるのか、その不安が大きい。
さて、干支九星から本年の年柄を見てみたい。
十干の甲は木気の陽(木の兄(え))。十二支の辰も春の後半から夏への入り口の土用を表わし、木気から一部土気に入るとき。九星は三碧とあって、これも木気。木気が三つ重なってまことに充実した生成発展の象である。
前回に木気が三つ重なったのは大正四年(一九一五)の乙卯四緑。その前は百八十年前の天保十五年(一八四四)甲辰三碧であった。それほど稀少の年である。天保の末といえば、幕府の体制の引締めを図るなかで開国を迫る諸外国が押し寄せ、幕末維新に至る動乱期の前夜のような時代状況であった。この年天保暦が施行され、現代にも用いられる、いわゆる旧暦はこれに基づいている。
十年ごとに最初に返る年である甲。植物の生長循環の過程では、固い殻を破って種子が発芽を始める状態。発芽から生育、開花、結実とすべての始まりである。
辰は震であり振である。「三月陽気動いて雷電震う、民の農の時なり(『説文』)」。万物振起するともいい、春の陽気が一段と盛んになり、あらゆるものが動き出す。草木が盛んに成長を始め、農事が始まる時を示している。農の文字の中に辰が含まれているが、辰の文字はもともと二枚貝の象形で、貝製の農具で草刈りを行ったことから農耕の意味を示す文字ができたという。ここからも辰が農事始めを表わすことにつながる。
三碧木星は震宮ともいい、雷電震うを表わした名称である。辰にも通じる。震というと地震を連想するかもしれないが、本来は激しい雷を意味し、強大なエネルギーをもって物事が揺れ動き、前進発展していくことを表わしている。春から夏へ、朝から昼へという五行の象意である。
辰の文字はまた、吉辰、佳辰ということばがあるように、時の意味にも用いられ、星の意味でもある。十二支のことを古くは十二辰ともいい、北極星のことを北辰ともいった。辰星とは二十八宿の房宿の異称であり、さそり座付近。その隣のさそり座の主星アンタレスを示す心宿の異称ともいい、その観測が農事始めの目標にもなっていた。
十二支の辰は想像上の動物である龍に結び付けられるが、なぜ辰が龍なのかよくわかっていない。ただ房宿は東方の守護神ともされ、朱雀・白虎・玄武とともに四神の一つである青龍の本体ともいうので、その関係はあるのだろう。近代以前は平安京の立地などでよく知られるように、四神相応の思想は都市計画などでも重視された。
龍神信仰は農耕社会、ことに稲作にとって非常に大切な水の確保にかかわるものであり、雨乞い行事は多くの地域に伝えられている。龍は雨を呼ぶといい、龍が暴れると豪雨をもたらすともいわれる。近年、豪雨災害が各地で毎年の例となり、その被害がまことに甚大だが、かつては米作りのために豪雨も時に必要と考えられたのが龍神信仰の一面であった。記紀にも龗(おかみ)の神として現われ、龍神信仰にかかわる神社は少なくない。このように木気ではあるが、水気とのつながりが多いのも辰の特質である。
辰の消長卦は
新型コロナの蔓延が一段落となり、多くの行事が四年ぶりに通常の態勢で行われたが、復活できないものや変容したものもあり、産業や社会構造の面でもコロナ以前に戻らない面も少なくないと思われ、新型コロナの蔓延は世界史の転換点であったといえるであろう。
本年は一回目の東京オリンピックが行われ、東海道新幹線が開通した昭和三十九年から満六十年。戦後復興を画したこの年から本卦返りを迎えることになった。
その六十年前の明治三十七年(一九〇四)は日露戦争の開戦の年であり、明治体制の絶頂期に至った時期ともいえる。さらにその十年前は日清戦争の開戦の年、十年後の大正三年は第一次世界大戦の勃発の年と、十年ごとに日本にかかわる戦争が起っている。
ウクライナ状勢は長期化、深刻化し、ロシアの所業には憤りやる方ないが、中台状勢への飛び火の懸念もあり、また世界大戦に拡大しかねない不安もあって対応は困難を極める。戦争終結後の復興には日本の戦後復興や震災からの復興の経験が期待されているが、それよりも終結に至る道筋を描くことができるのか、その不安が大きい。
さて、干支九星から本年の年柄を見てみたい。
十干の甲は木気の陽(木の兄(え))。十二支の辰も春の後半から夏への入り口の土用を表わし、木気から一部土気に入るとき。九星は三碧とあって、これも木気。木気が三つ重なってまことに充実した生成発展の象である。
前回に木気が三つ重なったのは大正四年(一九一五)の乙卯四緑。その前は百八十年前の天保十五年(一八四四)甲辰三碧であった。それほど稀少の年である。天保の末といえば、幕府の体制の引締めを図るなかで開国を迫る諸外国が押し寄せ、幕末維新に至る動乱期の前夜のような時代状況であった。この年天保暦が施行され、現代にも用いられる、いわゆる旧暦はこれに基づいている。
十年ごとに最初に返る年である甲。植物の生長循環の過程では、固い殻を破って種子が発芽を始める状態。発芽から生育、開花、結実とすべての始まりである。
辰は震であり振である。「三月陽気動いて雷電震う、民の農の時なり(『説文』)」。万物振起するともいい、春の陽気が一段と盛んになり、あらゆるものが動き出す。草木が盛んに成長を始め、農事が始まる時を示している。農の文字の中に辰が含まれているが、辰の文字はもともと二枚貝の象形で、貝製の農具で草刈りを行ったことから農耕の意味を示す文字ができたという。ここからも辰が農事始めを表わすことにつながる。
三碧木星は震宮ともいい、雷電震うを表わした名称である。辰にも通じる。震というと地震を連想するかもしれないが、本来は激しい雷を意味し、強大なエネルギーをもって物事が揺れ動き、前進発展していくことを表わしている。春から夏へ、朝から昼へという五行の象意である。
辰の文字はまた、吉辰、佳辰ということばがあるように、時の意味にも用いられ、星の意味でもある。十二支のことを古くは十二辰ともいい、北極星のことを北辰ともいった。辰星とは二十八宿の房宿の異称であり、さそり座付近。その隣のさそり座の主星アンタレスを示す心宿の異称ともいい、その観測が農事始めの目標にもなっていた。
十二支の辰は想像上の動物である龍に結び付けられるが、なぜ辰が龍なのかよくわかっていない。ただ房宿は東方の守護神ともされ、朱雀・白虎・玄武とともに四神の一つである青龍の本体ともいうので、その関係はあるのだろう。近代以前は平安京の立地などでよく知られるように、四神相応の思想は都市計画などでも重視された。
龍神信仰は農耕社会、ことに稲作にとって非常に大切な水の確保にかかわるものであり、雨乞い行事は多くの地域に伝えられている。龍は雨を呼ぶといい、龍が暴れると豪雨をもたらすともいわれる。近年、豪雨災害が各地で毎年の例となり、その被害がまことに甚大だが、かつては米作りのために豪雨も時に必要と考えられたのが龍神信仰の一面であった。記紀にも龗(おかみ)の神として現われ、龍神信仰にかかわる神社は少なくない。このように木気ではあるが、水気とのつながりが多いのも辰の特質である。
辰の消長卦は
であり、一陰五陽、沢天夬(たくてんかい)として表わされる。夬は決の旁で、決断の決である。上に残る陰の気に対して下から陽の気が持ち上って全陽に向って押し上げようとする寸前。天上の沢から水が溢れ出るというと、堤防が決壊して土砂災害になることを連想する人が多いであろうが、天子の恩沢が万民に及ぶことを表わすとされてきたのが古来の解釈であった。上方に残っている陰気とは邪悪害毒を意味し、陽の気たる正義正道が伸長して影響力が全般に及び、邪悪を放逐克服して正義を押し拡げ、また事業を遂行、進展させることを表現する。
このように、甲辰三碧の年は、殻を破って新たな生命力が芽生え、強大な力をもって成長進展していくことを表わしている。各自の志を堅く保って、周囲の抵抗に臆することなく、自信を持って目標とするところに邁進していただきたい次第である。
このように、甲辰三碧の年は、殻を破って新たな生命力が芽生え、強大な力をもって成長進展していくことを表わしている。各自の志を堅く保って、周囲の抵抗に臆することなく、自信を持って目標とするところに邁進していただきたい次第である。
(令和6年近江神宮『開運暦』より)